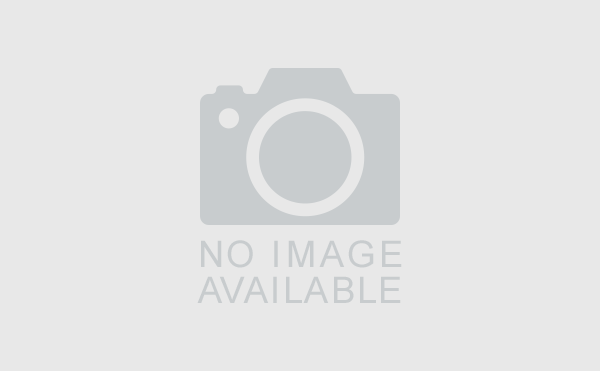vol.223 熱中症対策強化 ~ 事前の準備で酷暑による労働災害を防ぐ
2025年6月1日より労働安全衛生規則が改正され
熱中症対策が義務化されました。
具体的には、熱中症患者の報告体制の整備や、
熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、
それぞれ作業従事者に対して周知させなければなりません。
今回はどのように改正されたのか
熱中症予防対策や熱中症になった場合の手順等について
確認をしていきます。
■ 職場における熱中症とは
熱中症は、高温多湿な環境下において
発汗等による体温調節がうまく働かなくなり、
体内に熱がこもることで生じます。
職場における熱中症は、
屋外で作業する場合だけでなく
湿度の高い室内でも発生しますので
室内作業を行っている労働者も注意が必要です。
《熱中症が疑われる症状の例》
○自覚症状
めまい、頭痛、不快感、吐き気、こむら返り
高体温、何となく体調が悪い、すぐに疲れる 等
○他覚症状
ふらつき、生あくび、イライラしている、フラフラしている、
大量の発汗、けいれん、呼びかけに反応しない、ボーッとしている 等
意識があったとしても、返事がおかしい等、
いつもと様子が違う場合は
「異常あり」と取り扱うことが適当だとされています。
おかしいな、いつもと違うな、と感じたり
他の人の行動が自分とは違う、おかしいと思ったら、
早めに管理者に報告しましょう。
■ 労働安全衛生規則の改正
今回の改正では、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、
熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、
迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、
事業者に対し、以下の点を義務付けます。
・早期発見のための体制整備
・重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
・関係作業者への周知
近年、熱中症による死亡災害は年間 30 人を超え、
労働災害による死亡者数全体の約4%を占めていることを受け、
熱中症対策の強化が急務とされています。
そのほとんどが、「初期症状の放置・対応の遅れ」と言われており
これに対し明確な規定がないことが問題視され、
今回の改正となりました。
■ 熱中症対策強化の内容
●熱中症対策が義務づけられる業務・作業
対象となる作業は、
WBGT値(暑さ指数)28度以上
または気温31度以上の環境で、
連続1時間以上
または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。
WBGT値とは
(Wet Bulb Globe Temperature 湿球黒球温度)
気温に加え、湿度、気流、
輻射熱(地面や建物・体から出る熱)を考慮した
暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数をいい、
ISO等で国際的に規格化されています。
~厚生労働省パンフレット P.2
表1-1 身体作業強度等に応じたWBGT基準値~
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
~熱中症予防情報サイト 暑さ指数の実況と予測~
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php
●会社に求められる対策
上記条件に当てはまる作業をおこなう会社は
①報告体制の整備
②実施手順の作成
③関係者(労働者)に周知
をおこなう必要があります。以下詳しく見ていきましょう。
①報告体制の整備
熱中症のおそれがある作業を行う際は、
「熱中症の自覚症状がある労働者」
「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
が、その旨を速やかに報告できる体制を
整備しておくことが求められます。
具体的には、報告する連絡先(電話番号、メールアドレス等)や
担当者を決める必要があります。
また、熱中症の症状がある労働者を積極的に把握できるよう
職場巡視やバディ制度の採用、
ウェアラブルデバイス
(手首や腕、頭などに装着するセンサー、機器)等の活用、
双方向での定期連絡、などの措置が推奨されています
②実施手順の作成
熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に、
迅速かつ的確な判断が可能となるよう
あらかじめ対応手順を整備しておく必要があります。
具体的には、以下のような措置について、
事前に内容を明確にし、
実施手順として文書化しておくことが重要です。
《対応手順の例》
1.作業からの離脱
2.身体の冷却
3.必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
4.事業場における緊急連絡網、
緊急搬送先の連絡先および所在地等の確認と共有
《現場での応急処置の例》
・涼しい場所への移動
風通しのよい日陰やエアコンの利いた室内などの
涼しい場所へ移動させる
・身体の冷却
衣服をゆるめ、氷やアイスパックなどで体を冷やす
(特に首の回り、脇の下、足の付け根等)、
水をかけて全身を急速冷却する
・水分、電解質の補給
水分・塩分、経口補水液等を補給させる
ただし、水分補給の際、「意識がない」
「呼び掛けや刺激に対する反応がおかしい」等の時には
無理に飲ませてはいけません。
(誤って水分が気道に流れ込む可能性があるため)
ただちに救急隊を要請してください。
なお本措置は「事業場」単位ではなく
「作業場」単位で講じる必要があります。
③関係者(労働者)に周知
整備した報告体制や実施手順は、
関係者全員に周知させる必要があります。
朝礼やミーティングでの周知、
会議室や休憩室などわかりやすい場所への掲示、
メールやイントラネットでの通知などを通して
社内で共通認識を持てるようにしましょう。
■ 熱中症予防対策
「職場における熱中症予防基準対策要綱」では、
WBGTを活用すること、
作業環境のWBGT値が身体作業の強度ごとに設定された
WBGT基準値を超える場合には
熱中症予防・対策を実施することが求められています。
1.作業環境管理
作業場や休憩所を管理し、負荷の少ない環境を整える
・作業場のWBGTの低減(直射日光・照り返しの遮蔽等)
簡易的な屋根を設けて直射日光を当てないようにする等
・冷涼な休憩所の整備等
高温多湿な作業所の近隣に冷房を備えた
休憩場所や日陰等の涼しい休憩所を設ける
2.作業管理
作業時の時間や管理、水分・塩分摂取、巡視を行い、
熱中症リスクを低減する
・作業時間の短縮
・暑熱順化(体を暑さに慣れさせること)
・水分・塩分の定期的な摂取
自覚症状の有無にかかわらず、水分および塩分を
作業の前後や作業中の定期的な摂取を指導
・服装の注意(透湿性・通気性の良い服装)
・作業中の巡視
3.健康管理
事前の健康管理とともに、作業時の健康状態を確認し、
熱中症の発症を防ぐ
・健康診断結果に基づく対応
・日常の健康管理
睡眠不足、体調不良、前日の飲酒、
朝食の未摂取などは熱中症リスクを上げる恐れあり
・健康状態・身体状況の確認
4.労働衛生教育
作業者・管理者自身に対して安全衛生教育を通して
熱中症に関する情報の共有・啓発を行なう。
・熱中症の症状
・熱中症の予防方法
・緊急時の応急処置
・熱中症事例
まずは、熱中症をおこさない、ことが重要で
もし熱中症の症状が疑われる場合には
早めに対応することが、大きな事故を防ぐことになります。
~厚生労働省パンフレット
働く人の今すぐ使える熱中症ガイド~
https://neccyusho.mhlw.go.jp/download/assets/pdf/guide_pdf_all.pdf
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ここが知りたい! Q&A
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【Q.1】
熱中症になりやすい業種はどのようなものがあるでしょうか。
【A.1】
屋外で働く建設業や警備業、
農業や林業の第一次産業などはもちろんのこと
製造業も死傷者数が多い業種です。
また営業で外回りをしている方も熱中症になりやすいといえるでしょう。
年齢が高い方、持病がある方も熱中症になりやすいと言われています。
熱中症は例年、6月から9月に集中しています。
これらの災害の中には気温が30℃未満でも、
湿度が高いときに発生した例があり、
北海道や東北地方を含めて、全国で発生しており
高温で多湿な時には、どの地域でも、どの業種でも
十分な注意が必要です。
☆ ☆ ☆
【Q.2】
今回の熱中症対策の改正で会社側が対策を怠った場合
罰則などはあるのでしょうか。
【A.2】
会社が対策を怠った場合は、
6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
(労働安全衛生法第119条)
対象となる作業や、熱中症になった場合の報告体制や手順を
早めに確認、作成しておきましょう。