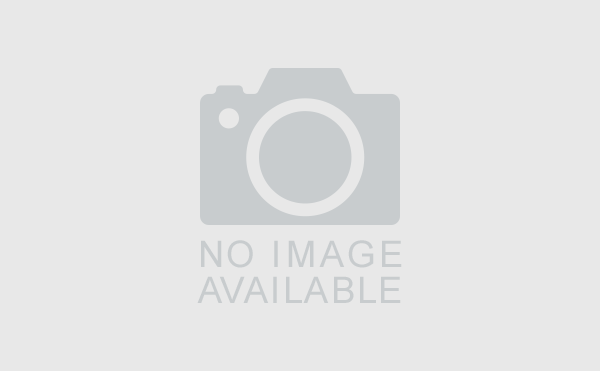vol.224 休職者の取扱い ~きちんと規定、正しい運用でトラブル回避
体調不良である程度長い休みを取る場合、
就業規則で「休職」の規定を設けている会社が多いと思います。
休職については、法律の定めがないことから
会社側で規定することが可能です。
ただし法律がない分、きちんと規定し運用しないと
トラブルになる場面も多く見受けられます。
今回は休職の取り扱い、また復職の際の注意点を
確認していきます。
■ 休職とは
休職とは、
「労働者の希望により会社の許可を得て、
長期にわたり労働を免除してもらう制度」
のことです。
あくまで自己都合で休む場合であり
会社の都合で休む場合は含まれません。
休職について定める法律がないため、
会社で休職制度を設ける場合は
就業規則で内容を明確に定めることが必要となります。
■ 休職、欠勤、休業の違い
欠勤や休業も「会社を休む」という点では
休職と同じですが、何が違うのでしょうか。
●休職
労働者側の個人的な事情によって、
会社から「労働の義務を免除される」ことを言い、
会社の許可を得ることが必要です。
●欠勤
労働の義務があるにもかかわらず
何らかの事情で労働者が仕事を休むことであり
「労働の義務が免除されない」ことが大きな違いです。
●休業
主に会社側の都合や
法令の規定を理由として「労働の義務が発生しない」点が異なります。
■ 休職の種類
休職の種類はいろいろありますが
今回、主な休職の一部を確認していきます。
●私傷病休職
労働者本人の健康上の理由により、
長期間にわたり就労困難な場合に休むことを
会社が認めるもの
●出向休職
会社に籍を置いたまま他社へ出向する場合
もともとの籍のある会社においては休職扱いとする
●起訴による休職
犯罪の疑いで労働者が起訴された場合に、
刑事処分が確定するまでの間、休職扱いとする
●自己都合休職(私傷病以外)
私傷病以外の私的な事情により休む場合
例えば、留学、災害支援復興ボランティア参加のため、
等が該当します。
こちらはあくまで一例であり、
会社で別の休職を設定しても
就業規則に記されていれば問題ありません。
■ 休職の手続き
労働者を休職させる手続きは下記の流れになります。
なお今回は、私傷病での休職を想定して説明します。
1.労働者からの休職の申し出
労働者が体調不良で労務が提供できない場合等は、
医師の診断書を提出してもらい、
休職の申し出を受けます。
なお、労働者の申出がない場合でも、
就業規則に定める要件に該当する場合は、
会社の判断で労働者に医師の診断書を提出してもらい
労働者を休職させることができます。
2.休職の検討
労働者からの申し出等により
就業規則の休職の要件に合致するかどうか確認し、
休職の判断をします。
3.休職の判断
検討の結果、休職が適正・妥当と判断した場合は、
会社より「休職発令書」を交付します。
休職発令書には、就業規則の「休職」に則り
休職の期間、休職期間満了日、賃金は有給か無給か、
本人負担分の社会保険料等の支払い方法、
休職中の過ごし方、会社への連絡方法と回数、等を
通知します。
■ 休職中の給与等
休職中の労働者に対し、会社は賃金を支払う義務を負いません。
これは「ノーワークノーペイの原則」によるもので
労働していない期間の分の(ノーワーク)
賃金を支払う必要はない(ノーペイ)とされているためです。
このことから一般的には、休職中は賃金を支払いません。
そのため、私傷病休職であれば、生活が困窮しないよう健康保険の
「傷病手当金」の申請をしている方が多いです。
もちろん休職中に賃金を支払ってもよいのですが、
その場合には、いつまで支払うのか、どのくらい(何割)支払うのか
等を決めておいたほうよいでしょう。
賃金から控除されている
所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料については
一部支払いが必要なものがあります。
所得税と雇用保険料は
発生した賃金に対してかかるものなので、
賃金が支給されない場合には控除の必要がありません。
一方、社会保険料は賃金が支給されているかどうかにかかわらず、
加入し続ける限り保険料が発生、支払が必要です。
また住民税は前年の所得に基づいて課税され、
賃金から天引きするのが一般的です。よって、
社会保険料と住民税は休職者に支払ってもらう必要があります。
休職から復帰が短期間であれば、
復帰した際に、休職期間中の社会保険料と住民税を
支払ってもらえればよいのですが、
長期間の休職になると、復帰後にまとめて支払うことが
大変になってきます。
できれば毎月、社会保険料と住民税を休職者から
会社へ振り込み等で支払をしてもらうよう
休職者と話し合いのうえ、合意を得ておくことをおすすめします。
■ 休職中の注意
休職発令により、休職に入る労働者に対して
いくつか注意する点があります。
引き続き私傷病休職を例として見ていきましょう。
1.休職中の過ごし方
休職期間は
「職場復帰するために体を休め、療養してらうための時間」
ということを認識してもらい、療養に専念するよう伝える。
傷病休職の場合、
「労務の提供ができないことによる休職」
という前提があるため
休職中は療養に専念してもらうよう伝えましょう。
時々「仕事をしてないときは元気」という方もいますが、
あくまで職場復帰を目的として体を休める期間であることを
伝えてください。
2.会社に定期的に報告をする
現在の症状・状況はどうか、
治療は進んでいるか、薬は飲んでいるのか、気分はどうか、通勤できそうか、等
定期的に報告をしてもらうようにしましょう。
できれば、1か月に1回程度、面談ないしは電話をするとよいと思います。
3.復職に向けての相談
休職期間満了が近づいてくると、
復職できる状態まで回復しているのか、
復職できずに退職なのか、を判断する必要があります。
復職できる可能性がある場合は
・医師の診断書に「復職可能」と書かれているのか、
・会社で面談等をして、通勤できる状態か、業務を遂行できる状態なのか
等、確認をして
会社側が総合的に判断をして復帰させるかどうかを
決定してください。
医師が「復職不可」と診断されている場合には、
会社側が「復職させたい」としても
復職させることはできません。
復職が難しい場合には
そのまま退職となります。
就業規則に「復職できない場合には自然退職とする」
と記載があれば、自己都合と同じ要件での退職となります。
特に記載がなければ、解雇の手続きを取ることとなります。
■ 復職の判断
私傷病休職の労働者が復職するまでの流れは次のとおりです
1.復職診断書の提出
就業規則等で復職に際し、主治医の診断書の提出を
復職要件としている場合には診断書を提出してもらうよう
労働者に伝えます。
ただし主治医が発行する復職診断書では、
日常生活を送るのに差し支えない程度に
病状が回復したことを根拠に
「復職が可能」と判断される場合もあります。
日常生活と業務に従事できることはイコールではなく
別の判断が必要ですので
診断書だけでなく総合的に復職できるかどうかを
会社側が判断しましょう。
2.産業医面談
産業医がいる事業所については、
主治医の診断書だけでなく、産業医面談も実施しましょう。
主治医が会社の事業や労働者の業務に
必ずしも詳しくないためです。
3.復職判断の条件
適切に復職の可否を判断して、
職場復帰後の症状の再発や再燃を予防することが大切です。
復職判断の条件としては
・整ったリズムで生活できている
・職場復帰への意欲が見られる
・通勤の時間帯に問題なく通勤できる
・定時に勤務できる
・決められた勤務日に仕事ができる
・投薬等の影響がない
・休職前の業務が行える
・主治医から復職可とする診断書が出ている
・家族の支援を受けられる
等があげられます。
このような判断材料から、
復職させるかどうかを見極めます。
復職可能であれば、
いつからどのような業務に就いてもらうのか
出勤時刻や時短勤務は必要かどうか、
等 具体的なプランを決めていきます。
復職できない、と会社側が判断した場合には
前項3にて前述したとおり、
休職期間満了により退職、となり
退職の手続きをします。
復職は休職を発令するよりも
より慎重に行いましょう。
復職後に病気が再発するケースはよく見られます。
本来は回復していなかった、
復職したためにより悪化してしまった、
というケースもあります。
本当に復職できるのかどうか、医師の診断書をもとに
社内で慎重に検討・決定してください。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ここが知りたい! Q&A
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【Q.1】
精神疾患で私傷病休職していた労働者が
復職をしましたが、また体調が悪いようで
再度休職となりそうです。
休職期間は新たにカウントされるのでしょうか。
【A.1】
就業規則によります。
最近の就業規則では
「同一の傷病においては休職期間を通算する」
と書かれているものもあり、
同じ傷病で休職する場合には、前に休んだ期間と通算して
休職期間をカウントする場合があります。
とくに精神疾患においては
再発の可能性が高いため、
就業規則には、休職期間を通算できるように
記載しておいたほうがよいでしょう。
☆ ☆ ☆
【Q.2】
復職後、会社として注意すべきことがあれば
教えてください。
【A.2】
復職したからといって、
必ずしも休職前と同じ状態に戻っているとは限りません。
人によって症状は異なります。
復帰して少し仕事に慣れてきたら
一度面談をするとよいでしょう。
きちんと睡眠はとれているのか、投薬の影響はないのか、
疲れやすい時間帯などがあるのか、
仕事を始めてみて新たに把握・自覚した点を
会社と労働者が互いに確認することが重要です。
また当分の間、
残業などは免除するなど無理のない程度で就労、徐々に仕事に慣れて
数カ月を目安に休職前の業務に戻れるように
していくことも考慮してもよいかと思います。
さらに、当該労働者だけでなく、
同じ部署や周りの労働者にも
業務の負担がかかっていることもあるため
復職者の周りの労働者へケアも必要でしょう。